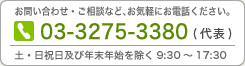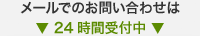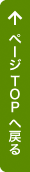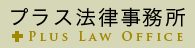第10回 建築業界の現状と将来(最終回)
欠陥住宅がなくならない理由
今回のコラムが最終回となります。これまで「欠陥住宅裁判で負けないための被害者の心得」について、基礎的なノウハウは一通りお伝えしてきましたので、最後は、欠陥住宅がなくならない「建築業界の現状と将来」について、私の考えをお話ししたいと思います。
過去にデータや性能の偽装などの欠陥住宅問題が幾度となく報道されて、その中には大手の会社が関与するケースもめずらしくなく、その都度社会の注目を浴びて、なぜ欠陥住宅がなくならないのかという議論が交わされてきました。
その問いに対する答えとしては、建築業界の構造的な問題を指摘する声が多く、その通りだとも思います。
しかし今回は少し切り口を変えて、制度面に着目して考えてみたいと思います。
事前予防と事後救済の制度が十分に機能していない
欠陥住宅問題は、報道で取り上げられるようなデータや性能の偽装などの「故意」によるものに限りません。私がこれまで取り扱った事案では、「故意」による悪質なケースはほんの一握りでして、それ以外は「過失」による設計ミスや施工不良などが大半を占めていました。ですから、悪質な欠陥住宅が多いかといえば、そうではないと思いますが、「過失」を含めると欠陥住宅の件数は依然として多いものといえるでしょう。
これはある程度仕方のないことで、建築は、工場などで機械的に組み立てられる自動車等の工業製品とは異なり、最終的には現場で人が部材を組み立てる必要があり、それぞれの地形に適した、注文者の意向に沿った一品物を建築し、その作業に関わる職人の数も多いため、どうしてもヒューマンエラーによる欠陥が生じやすいものなのです。
ヒューマンエラーが起きやすいことを前提とすれば、欠陥住宅の事前予防の制度がとても重要となってきます。現状では、建築確認、中間検査、完了検査などの制度があります。
ところが、主に設計のチェックを行う建築確認は、現在は「性善説」で制度運用されています。例えば、特定の条件を充たす小規模な建築物は、建築士が設計を行っていれば、いわゆる4号特例により、構造強度をはじめとする建築基準法上の審査が省略されることになり、関連する設計図書の提出も不要となります。これは、小規模な建築物で建築士の設計に係るものであれば、適切に設計されているであろうという「性善説」の考えによるものです。
しかし、過去に、建築士による構造計算書偽装事件が発覚して社会問題となりましたので、そもそも事前予防の制度が「性善説」で良いのか疑問があります。仮に百歩譲って、建築士が「故意」に欠陥住宅を設計しないと想定したとしても、「過失」による設計ミスは避けられないはずです。有資格者であってもミスはします。思い違いや技量不足などのケースもあるでしょう。このような事態に対して、現状の建築確認の制度ではチェック機能として不十分です。
また、施工のチェックとしては中間検査や完了検査などがあります。
しかし、いずれも確認できる範囲やタイミングなどが限られているので、確認できない部分の施工不良を未然に防ぐことはできません。過去には大手企業が関わる杭データ偽装事件や小屋裏界壁がないなど数多くの重大な施工不良が発覚して社会問題となりましたが、いずれも当時の中間検査や完了検査の対象外でした。
これら検査では施工過程を網羅的にチェックすることができないので、建築士法では、一定規模の建築物の工事監理(工事を設計図書と照合し、それが設計図書どおりに実施されているかを確認すること)を建築士の独占業務として定めました。ここでも、建築士によるものであれば、適切な工事監理が行われるものと期待されているわけです。
しかし、先に挙げた小屋裏界壁がなかった事例では、不祥事を起こした会社の外部調査委員会の調査の結果、会社の施工物件が年間700〜1,100棟に達していた時期に、工事監理を実施できた有資格者がわずか4〜25名に留まっていたというのです。いかに有資格者であったとしても、このような仕事環境では適切な工事監理を行えるはずがありません。
また、建築士法上の工事監理は「第三者性」を要件としていないので、自身が行った施工や自社施工でも、建築士であれば工事監理者となることができます。このような場合には、自分で自分の行いをチェックするようなものですから、厳しいチェック機能を期待することは難しいでしょう。
このように、現状の制度では、欠陥住宅の事前予防としての機能を十分に果たすことはできません。
では、事後救済はどうでしょうか。因果応報、欠陥住宅を生み出せば、必ずその責任を追及される。仮に事前予防が十分に機能していなくても、事後救済が上手く機能すれば、事後的に被害は回復されて、悪質な業者は自然淘汰されることが期待されます。これは主に司法の場面になります。
この点は、コラムの第1回でご説明したように、被害者側が立証責任を負わされている現状では、専門性の高い建築訴訟で欠陥の立証責任を果たすことは容易ではなく、また、欠陥は建物の内部や地盤の中など目に見えない箇所にあることが多く、それを調査するには専門家の協力が必要になるなど、立証すること自体の苦労もあるので、欠陥住宅裁判で被害者側が勝つのは一般的に難しく、事後救済も困難な状況です。
では、事前予防と事後救済の制度が十分に機能しない業界はどうなるのでしょうか?
故意に欠陥住宅を生み出して不当な利益を得るような悪質業者であっても、事前にその行為を止めることが難しく、事後的な責任追及も困難というのであれば、何とか生き長らえることができるでしょう。同様に、技術力がないなどの理由で頻繁に欠陥住宅を生み出してしまうような業者であっても、自然淘汰されにくい業界であるといえるでしょう。
こうした現状のため、欠陥住宅はなくならないのだと考えています。
建築業界の将来
このように暗い現状の話をするときには、建築業界の関係者の方から、「そんなことはない。日々真面目に仕事に向き合っている技術者は大勢いる。」とお叱りを受けることがあります。私もそのご意見には大いに賛成します。
しかし反面、先に述べたような、欠陥住宅がなくならないという問題を抱えていることも事実です。そして、この問題に向き合わなければ建築業界は改善されません。それによって一番の被害を受けるのは、不幸にも欠陥住宅を掴んでしまった消費者です。また、欠陥住宅がなくならないことで、建築業界に対する信頼が損なわれれば、真面目に仕事に向き合っている技術者の方々も、間接的に被害を受けることになります。
これは誰が悪いという問題ではなく、建築業界を向上させるために、いかにして消費者に安全な住宅を届けるかを目標に、行政、立法、司法、建築業界の全ての関係者が、皆で知恵を出し合って横断的に考えていかなければならない問題なのだと思います。
そのためには事前予防と事後救済の制度をいかに充実させるかが重要です。
事前予防としては、建築確認、中間検査、保険の検査、工事監理、どの制度を拡充するのでも良いですが、「第三者」が設計内容や施工過程の全体をしっかりチェックできる仕組み作りが必要です。そして、チェックする担当者が何らかの問題点を指摘した場合には、それが是正されるまでは工程を止められるほどの強い権限が必要です。さらに、チェックする担当者が公正な判断ができるよう、その担当者の地位や待遇などをしっかり保障してあげることも重要です。
事後救済としては、司法による積極的な被害救済が必要です。コラムの第1回でご説明した「立証責任」の事実上の転換などが一例です。最近の欠陥住宅裁判では、裁判所から、お互いに譲歩する和解を勧められることが多い印象ですが、それは「立証責任」が被害救済の壁になっているからなのでしょう。
今後も私は司法の現場から、建築業界の向上を期待して、欠陥住宅被害の予防と救済の活動を続けてまいりたいと思います。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。